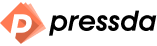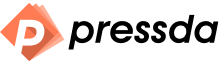植田総裁は、生鮮食品を含む食料品など人々の購入頻度の高い品目の価格上昇によって、消費者物価の総合指数が前年比で2%を超えているとし、「国民生活に強いマイナスの影響を及ぼしていることは深く認識している」と語った。
その上で、こうした食料品の値上がりが必ずしも一時的なものではない可能性にも言及。「人々のマインドや期待物価上昇率などに影響を与えるリスクはゼロではない。そうした観点も取り入れて適切に政策運営していく」と述べた。
日銀は1月に政策金利を17年ぶりの0.5%程度に引き上げ、経済・物価が見通し通り推移すれば利上げで金融緩和度合いを調整する方針を維持した。市場の関心は次の利上げの時期とペースに集まっている。日銀は物価見通しの作成では、振れの大きい生鮮食品を除くコア指数を示しているが、総裁は生鮮食品を含めた物価上昇の動向を注視していく考えを示した。
総務省が先月発表した昨年12月の全国消費者物価指数(CPI)は総合が前年比3.6%上昇と2023年1月以来の高い伸びとなった。生鮮食品は17.3%上昇した。生鮮食品を除くコアCPIは3.0%上昇し、1年4カ月ぶりの3%台乗せ。生鮮食品を除く食料は4.4%上昇となった。
植田総裁は、利上げ幅を小さくして柔軟性や機動性を高めるのも一つの方法ではないかと問われ、どの程度の幅でやるべきかはその時々の経済・物価・金融情勢次第と説明。1月に実施した0.25ポイントの利上げに関しては、「これまでのところこうした利上げの幅による政策決定は適切であった」との認識を示した。
米国のトランプ政権の政策運営に関しては、米国経済だけでなく世界経済や市場に大きな影響を及ぼすとし、「非常に高い関心を持ってみている」と言明。その上で「米国の政策が一段と明らかになるにつれて、われわれの見通しにもしっかりと取り込んでいきたい」と述べた。
ブルームバーグが1月利上げ後に行ったエコノミスト調査では、政策金利を0.75%程度に引き上げる時期は7月が56%と最多となっている。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement